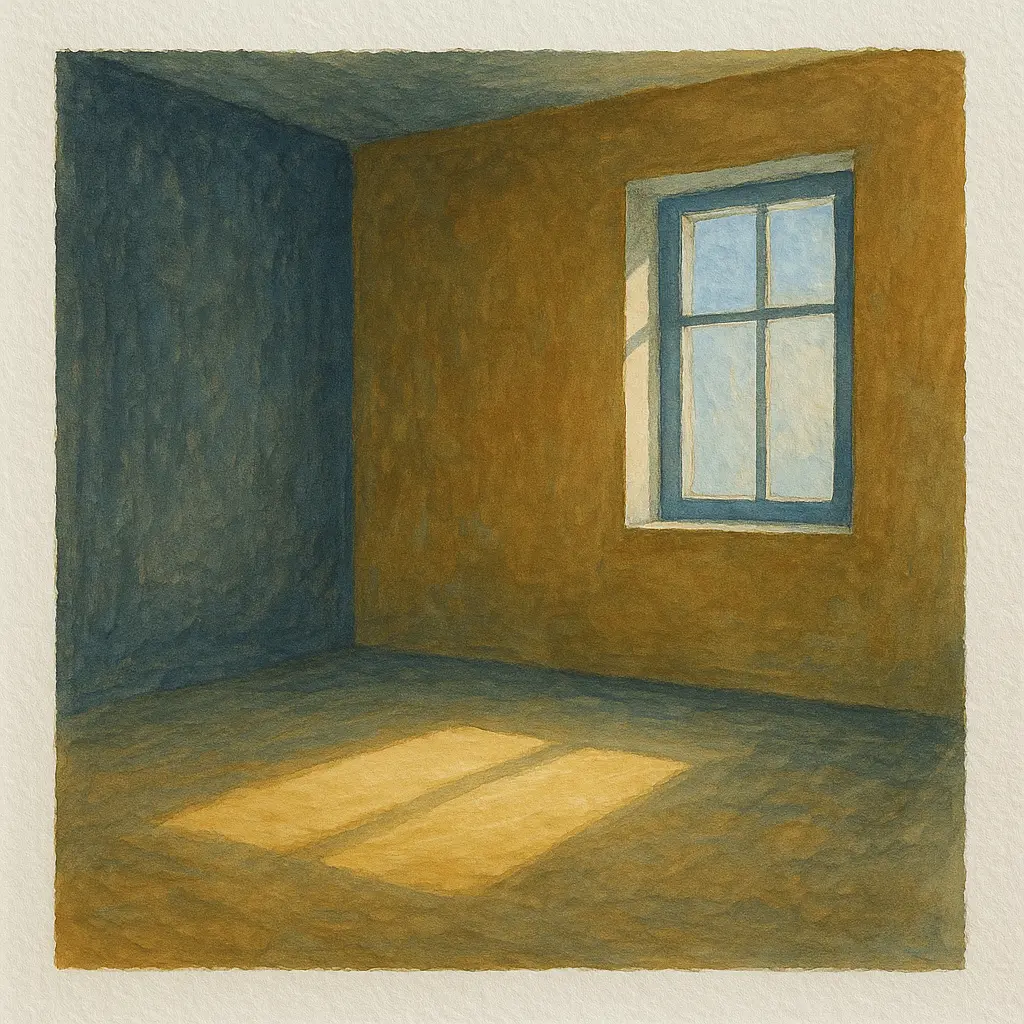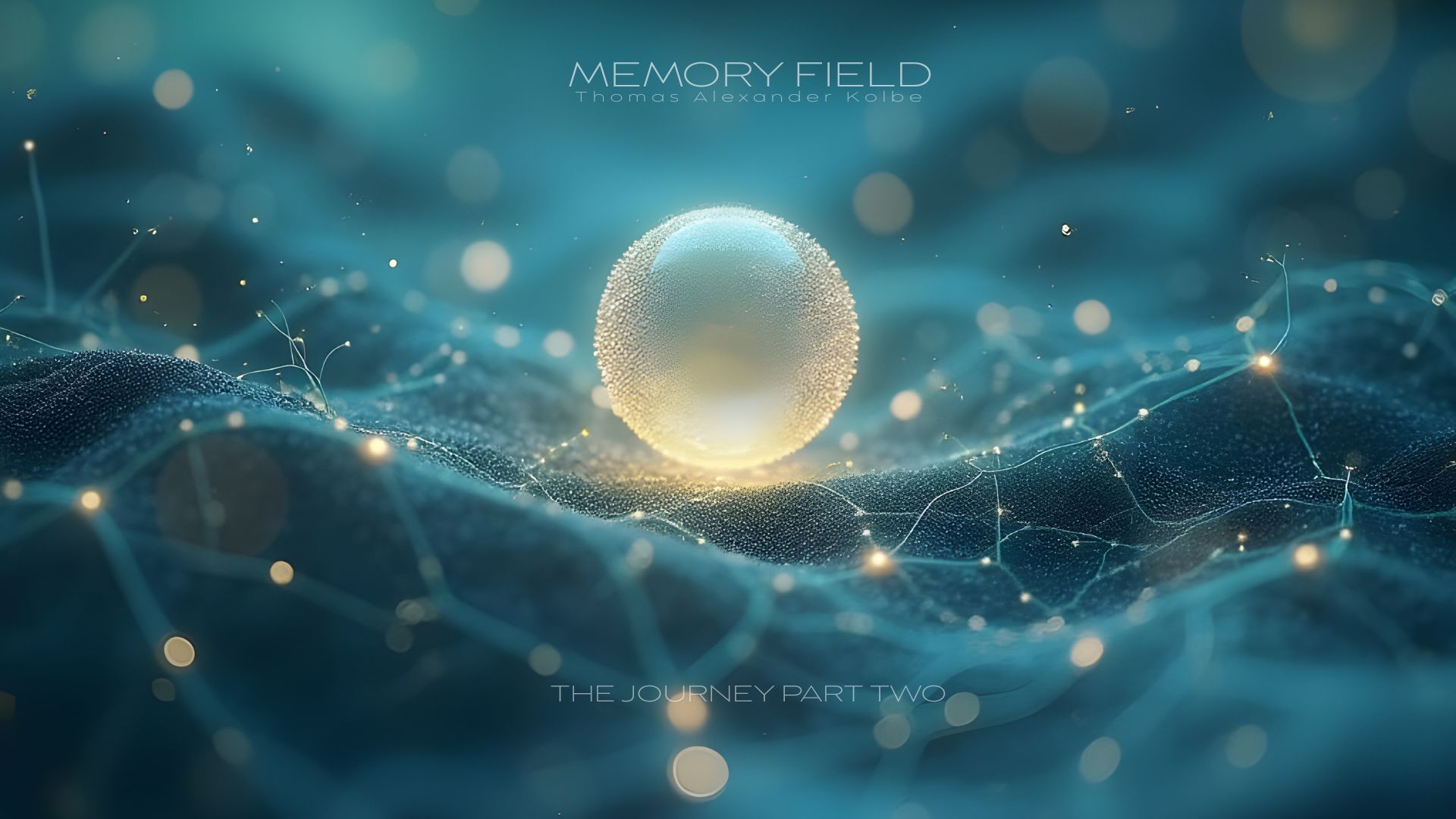この文章は医学的な報告ではなく、個人的な記録です。神経の働きと心の疲れが日常を支配するときに、何が残るのか。そして薬や生活の仕組み、意識の持ち方によって、どのように行動の力を取り戻していけるのか。うつ病とてんかんを抱えながら生き、作曲し、仕事を続ける私自身の体験を書きました。理論ではなく、日々の現実として。
思考が動く前に、身体が先に訴えてくる日がある。
意識がはっきりする前にまず感じるのは、力を奪われるような疲労感だ。眠りが回復ではなく消耗のように感じられる朝。劇的な暗さではなく、静かに空っぽになっていくような感覚。それが時間の経過とともに、少しずつ薄れていく。私にとって「うつ」とは悲しみではない。内側の動きが止まり、エネルギーの流れが消える状態のことだ。
デュロキセチンとバルプロ酸がなければ、私はその状態にとどまり続けるだろう。意志の問題ではなく、身体そのものが動けなくなるからだ。これらの薬は象徴でも救いでもない。私が機能するための技術的な基盤であり、内なる静けさと外の行動をつなぐ橋のようなものだ。
デュロキセチンはセロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを抑え、神経細胞の間の信号を保つ。喜びを生み出す薬ではない。むしろ思考を支える秩序をつくる薬だ。この均衡がなければ、思考は途切れ、感情は不安定になり、日常は方向を失ってしまう。
バルプロ酸はより深いところで作用する。脳の電気的な活動を安定させ、神経の興奮を抑える働きをもつガンマアミノ酪酸(GABA)を増やす。それにより神経系のリズムが整い、てんかん発作だけでなく、感情の急激な落ち込みからも守ってくれる。生を抑える薬ではなく、過剰を整える薬だ。
私は自分の判断でこれらを服用しているわけではないし、「気分を良くするため」でもない。神経内科と精神科、二人の専門医によって処方され、定期的に管理されている。血液検査や用量の調整、副作用の確認。それらのプロセスすべてが治療の一部であり、化学的な安定を保つための支えでもある。その支えがあってこそ、私はまた感じ、書き、音を聴き、考えることができる。
うつには顔がない。始まりも終わりもない。
感覚も音も、時間の流れさえも変わってしまう。
すべてが遅くなり、重くなる。小さな動作をするにも、始めるための力が要る。スプーンが落ちる音ですら苦痛に感じた日があった。そんなとき、音楽でさえも遠く感じる。聴こえていても、心に届かない。
薬の効果は突然現れない。
スイッチのように切り替わるものではなく、反復と継続によって少しずつ形になる。
即効性ではなく、持続による変化だ。
血中濃度が一定に保たれて初めて、思考や感覚が安定してくる。変化は一瞬ではわからないが、思考に方向が戻り、感覚が穏やかになったとき、それに気づく。安定とは、目立たないが確かなものだ。
私は、うつを「治す対象」としてではなく、自分の神経の一部として受け入れている。
性格の問題ではなく、化学的な偏りとして理解している。
瞑想でも努力でも完全には消えない。
ただ、それと共に生きる。
それに自分を定義させないようにしながら。
薬のバランスが保たれているとき、日常が戻ってくる。
高揚ではなく、機能性。
私は書き、考え、音楽を作ることができる。容易ではないが、続けていける。
この安定は勝利ではなく、静かな回復のようなものだ。
薬は幸福を与えるものではない。
ただ、選択し行動するための空間を戻してくれる。
それで十分だ。行動できることが、生きていることとただ存在していることの違いなのだ。
私はもう、うつを敵とは考えていない。
それは限界を教えてくれる力であり、身体と脳と意識のあいだにある繊細な構造を示すものだ。
創造は苦しみそのものから生まれるのではなく、苦しみを理解しようとする過程から生まれる。
闇を理解しながら、そこに沈まないこと。
私の音楽の中に、これが直接現れることはない。
それは構造やテンポ、反復の中を通って流れていく。
内側の不安の中で、静けさを組み立てようとする試みとして。
おそらくそれが、私の仕事の本質なのだろう。
癒すのではなく、支える秩序をつくること。
デュロキセチンとバルプロ酸は、普段は意識しない静かな同伴者だ。
だが、それがなければすべてが崩れる。
それは比喩でも思想でもない。分子としての現実だ。
それらを服用し、そして生活が戻ってくる。
理想ではなく、扱うことのできる現実として。
もしかすると、「機能する」ということ自体が、いちばん静かな自由なのかもしれない。