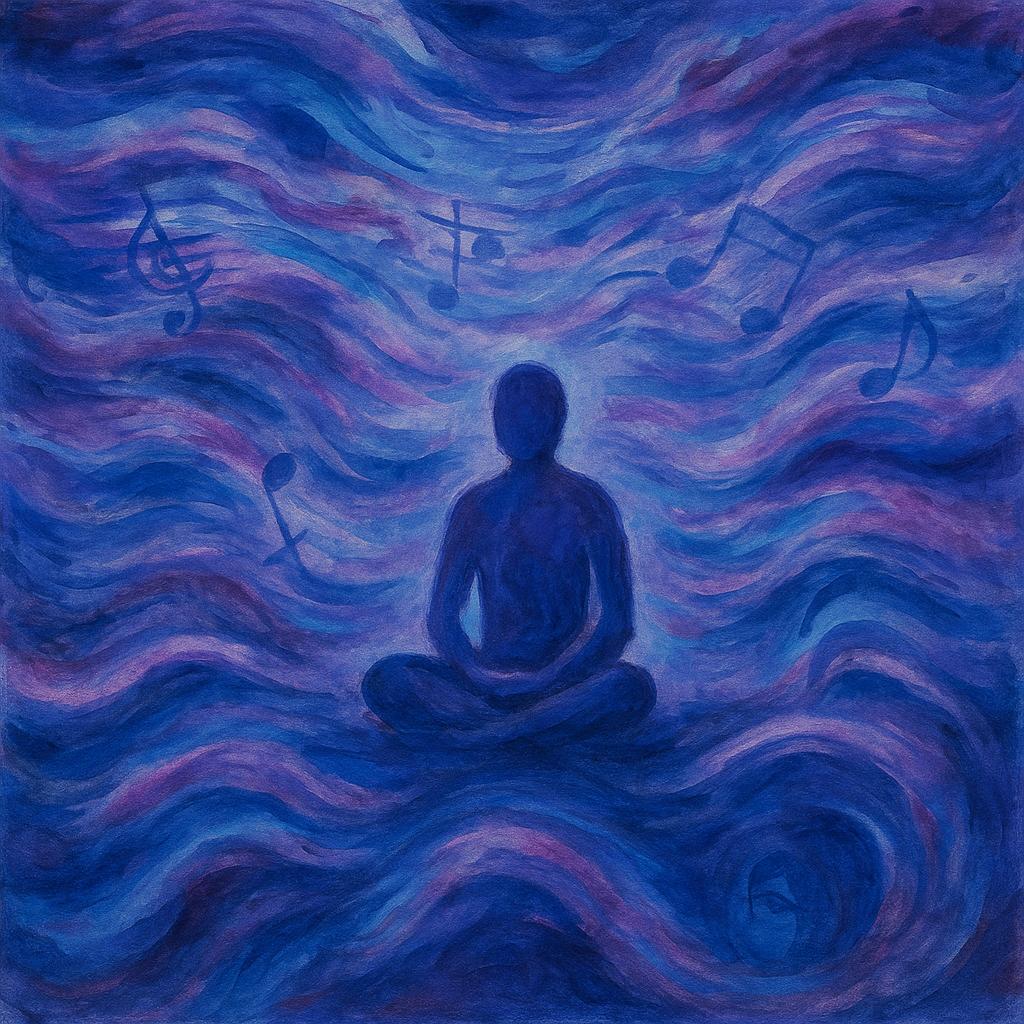朝、私はピアノの前に立ち、まだ薄明かりの中に漂う視線のまま、ある言葉を思い出す。「今日という日がどのように展開するのか、私は知らない。」まさにこの瞬間から、私の音楽的な営みが始まる。それは形式と自由が絶えず交錯する対話的な過程である。作曲とは、固定された構造を作ることだけではなく、今という時間の中で展開する動きに身を委ねることだと私は学んできた。それは、どこにもとどまることのない川のようだ。
毎日は新しい可能性を運んでくる。音で満たされるのを待つ空白のキャンバスのように。鍵盤に指を置く前に、私はしばし静寂の中にとどまり、その日の空気や色を感じ取ることが多い。窓から差し込む光が部屋の雰囲気を変えることもあれば、外の世界の音が方向を示してくれることもある。インスピレーションはどこからでもやってくる。本棚に詰まった物語や知恵、壁に掛けられた絵画が秘める静かな語り、そして心の奥に静かに眠る記憶たちから。
即興をするとき、私は本質的なものと向き合っている。空間の響き、自分自身の呼吸の微かな振動、そして音の微細なニュアンス。私はあらかじめ決められた線を描くのではなく、すべての動きを問いかけであり、同時にその答えとみなす。鍵盤の上の手は、聴くための器官となる。私は楽器の発する音だけでなく、自分の内側、意識的な思考の彼方から湧き上がる衝動に耳を傾ける。そうして音楽は、瞬間ごとに姿を変えながら、進行してゆく創造の流れとして現れる。
音楽は私にとって魂の鏡であり、深く隠された感情を表現し、整理するための道である。喜びのとき、音楽は光と動きに満ちて踊るようになり、悲しみのときにはゆっくりと慎重に流れる川のように変わる。選ぶ音、それらの組み合わせ、響き合いのすべてに感情が込められている。それはまるで音の風景を描き出すようであり、その中に私は沈み、身を委ねることができる。
作曲において、私は時に日本の美意識「序破急」に従う。静かな序章、変化による展開、そして加速された凝縮。私は静寂の中で始め、モチーフを曖昧にし、音高やテンポのようなパラメーターを開いたままにする。譜面を書くのは、何かを固定するためではなく、可能性を促すためである。そうすることで、譜面は生きたものとなる。自分自身で解釈する時も、他の演奏者が演奏する時も、譜面・空間・音の創造との間に絶え間ない対話が生まれる。
即興演奏は、私にとって最も純粋な音楽表現のひとつである。それは、瞬間と自分の直感を信じる深い信頼を必要とする。即興の中では、私はコントロールを手放し、音楽に身を預ける。どこに向かうのか分からない旅に出るようなものだ。すべての音が選択であり、すべての和音が分岐点。時に音楽は見慣れた場所へ、時に未知の領域へと導く。この不確かさこそが、即興の魅力であり、創造の源となる。
あるセッションを思い出す。私は断片的な楽譜だけを書き残した。演奏者たちはそれを、共に輪郭を描く風景への手がかりとして扱った。書かなかった部分が、各声部の相互作用から生まれてきた。譜面は命令ではなく、招待状となった。この「知らなさ」、意図的な「空白のままにしておく」姿勢こそが、創造的な方法だと私は考えている。それが驚きの余地を生み、思いもよらぬ音を引き出す。
中心的な要素として、私は「沈黙」を重視する。単なる無音ではなく、共鳴の空間としての沈黙。たとえば日本の笙による即興の伝統では、音の合間の沈黙は音そのものと同じくらい大切にされている。「間(ま)」を聴く練習を私は続けている。緊張、期待、余韻を内包するその間。作曲の際にあえて休止を設け、音と沈黙が交互に現れるよう構成することで、沈黙が音のキャンバスとなり、ひとつの音が完全に消えるまでの余白が生まれる。
私はまた、アレアトリック(偶然性)な手法にも取り組んでいる。サイコロを振ってパラメーターを決めたり、外部の偶発的な要素を創作に取り入れたりする。そうした中で、意図せず現れる音に驚かされ、自分では決して選ばなかった響きと出会うことがある。これらは、コントロールを手放すことの価値を教えてくれる。それは混乱ではなく、豊かさだと私は捉えている。慣れ親しんだ感覚を問い直し、論理的な思考を超えた音の可能性に触れる機会となる。
予測と驚きの関係を考えるとき、私は聴覚心理学の研究を思い出す。人は予想と現実のずれに対して反応し、そこに緊張が生まれるという。その仕組みを私は作品の中で用いる。たとえば親しみのある旋律を、突然予想外の和音に導いたり、リズムのパターンが認識された直後に崩したり。聴く者が常に「いま」に意識を向けるような音響の風景を描き出したい。
音楽は個人的な表現にとどまらず、聴衆との架け橋でもある。演奏するたびに、私は目に見えない糸で観客と結ばれる。その反応、沈黙、呼吸――それらすべてが演奏に影響を与え、その場限りの体験となる。音楽が観客の心に触れ、感情を呼び覚まし、記憶をよみがえらせるのを私は感じることがある。このやり取りこそ、演奏の中で最も美しい瞬間のひとつだと私は思っている。共に旅に出るような、そんな時間。
演奏とは、絶えず聴くことの行為でもある。自作にせよ他者の作品にせよ、私は音だけでなく、その背後にある語られないもの、響き合う層を聴き取ろうとする。技術だけでは足りない。空間に生まれる微細な変化、音と音の間の変化、響く身体、会場の音響、そして沈黙との関係性に敏感であることが求められる。
リハーサルでは、意識的に「共に聴く時間」を設ける。断片を演奏し、立ち止まり、聴き、語り合い、また演奏する。この共同的な聴き方によって、演奏の見え方が変わる。全員が創造に関与し、アンサンブルが音の探求の空間となる。
すべてのセッションの終わりにあるのは、完成された何かではない。響きと沈黙が空間に残る、その「今」こそが終わりである。作品が完成したという感覚ではなく、その演奏が無数の可能性の中の一つにすぎないことを私は感じる。音楽は記憶の中で続き、余韻の中で息づき、それぞれの聴き手の心の中で再生されていく。
音楽を通して、私は人生そのものがひとつの作曲であることを知った。それは常に生成し、移ろい、音と沈黙の交差である。毎日が新しい音と間、新しい可能性と挑戦をもたらす。そして私は、音楽の中で迷い、また見出し、人生の中でも繰り返し自分を再発見する。
私にとって音楽実践とは、開かれ続けること、不確かさに耳を澄ますこと、そして自己と世界との関係を絶えず更新し続けることに他ならない。音楽は第一音から始まるのではない。それは最初の「聴くこと」から始まり、聴かれるその瞬間ごとに、何度でも新たに生まれ直すのだ。
日々を重ねるごとに、音楽が私の人生に与える影響の大きさを実感する。それは職業ではなく、生き方そのもの、世界の見方であり、理解の手段である。音楽は私に忍耐と謙虚さ、そして開かれた心を教えてくれる。言葉にできない美しさは、往々にして予期しない瞬間や、音と言葉の間に潜んでいるのだということを。
だから私は、今日もまた朝、ピアノの前に立つ。音楽に導かれるために、耳を傾け、学び、自分自身と世界を新たに感じ取るために。なぜなら音楽の中に、私は表現だけでなく、(家族とともに)慰め、喜び、そしてすべてとつながる深い感覚を見出しているからである。